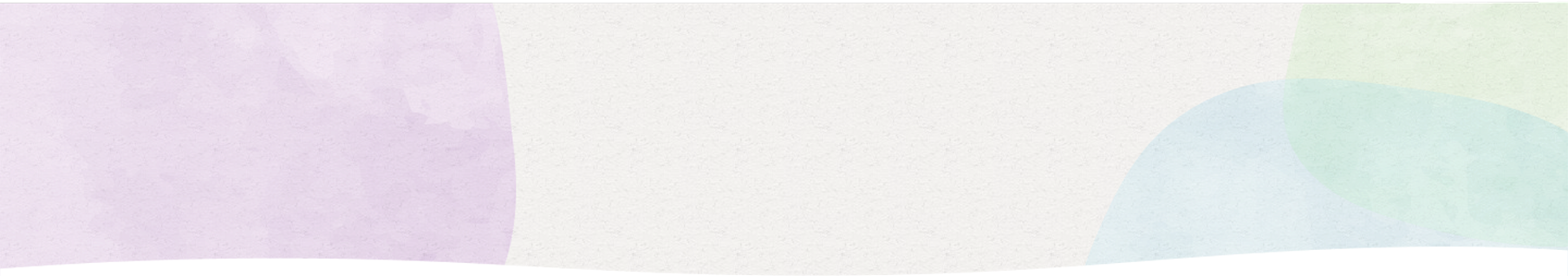ウイルス病について
ウイルス病とM.T.C.苗について
ブドウに関しては世界で80 種類ほどのウイルスが発見されています。その中には、糖度の低下、着色不良、収量減、衰弱短命などをもたらすものもあります。主なものはリーフロール(葉捲病)、フレック、コーキーバーク(樹皮のコルク化)、ファンリーフ(縮葉病)など 種の主要ウイルス病です。
また、ステムピッティング(枝幹異常症)は幹の粗皮を剥ぐと無数の穴や溝が生じているウイルスで、植え付け5 〜 6 年後に発生してだんだん樹勢が衰えます。本病は成長点組織培養苗には発生しません。
巨峰群品種では地域的にモザイク病が見られ、ハモグリダニによって伝播することがわかりました。
「M.T.C」苗とは、Mは成長点(Meristem)、Tは先端(Tip)、Cは(Culture)の頭文字をとったものです。
各種台木・各品種を、成長点頂部組織培養(M.T.C)技術により、各種ウイルスの生息密度が低い培養苗を作り出し、それを母樹に育ててから苗木を生産しており、その苗木のことを当社ではM.T.C 苗と呼称しております。
本サイトでは![]() で表記しております。
で表記しております。
ウイルス病の感染について
ウイルスは栽培年数を経過しますと再び感染するといわれています。接木感染はよく知られていますが、虫媒感染(クワコナカイガラムシ・ブドウハモグリダニ・ヨコバイ)、土壌感染、接触感染など、一部感染経路が分かった例もありますが、未知の分野もあります。当社では国の検定合格証明証を戴き、細心の注意を払って苗木を生産しておりますが、栽培を続けている間に、万一その樹がウイルスに感染した場合、その責任を全て当社が負うことは不可能です。
そこで、当社は最初に組織培養してからの年数が経過しましたので、数年前から生食用、ワイン用の主要品種や主要台木などの数十品種を選び、現在、再度の成長点組織培養を依頼しております。現在、順次、入手した培養樹を増殖中です。
組織培養は品種数も多く、経済的にも大変ですが、できる限りの努力はしておりますので、このような事情をご理解いただき、今後とも情報の交換など、ご協力、ご支援を伏してお願い申し上げます。
防除について
本年度から、諸般の事情により当品種解説中での防除暦の掲載が出来なくなりました。ご参考にしてきていただいた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解の程お願い申し上げます。尚、防除暦につきましては各県の関係機関で配布またはホームページ等で確認出来ると思いますので、そちらをご利用下さい。
高温多湿の日本においてブドウを栽培する場合、防除作業は必須であり年間約12 回程度の農薬散布が必要です。降雨等気象の条件による病気や害虫の発生状況によっては、回数を増やさなければ病虫害を防ぐことは出来ません。よく園を観察し、病虫害発生前の予防的防除を心掛けてください。病気の種類を見分けられない時や発見が遅れますと防除が手遅れになり、病虫害の広がりを抑えきれない場合も出てきます。
趣味栽培の方で休眠期防除を行わず、黒とう病やハモグリダニが発生してご質問をいただくケースも多く、病虫害が発生してから防除の大切さを実感される方も少なくありません。スリップスの被害なども見分けられずに被害果を送って来られます。防除のみでなく、専門書をよく読んで勉強しながらブドウ作りに挑戦して下さい。